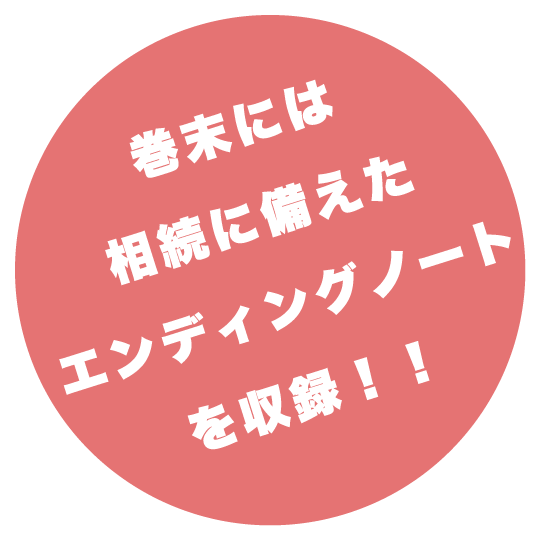堺市で弁護士に離婚問題・相続問題を相談するなら四ツ橋総合法律事務所 井筒壱弁護士へ
堺市で弁護士に離婚問題・相続問題を相談するなら四ツ橋総合法律事務所 井筒壱弁護士へ
堺市で弁護士に相談するなら
Yotsubashi Law Office.

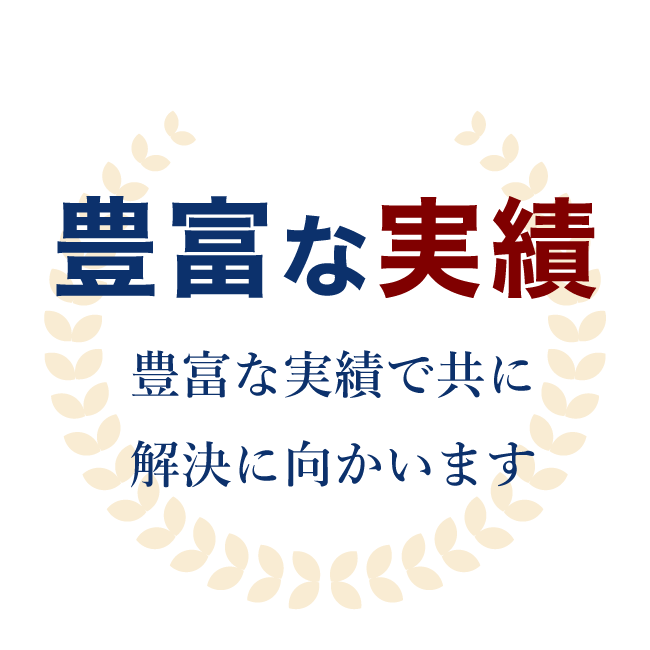
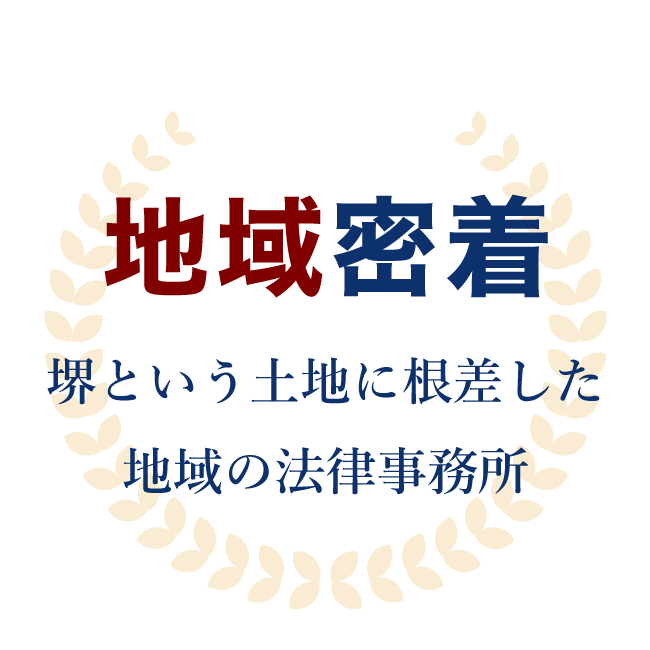
離婚は当事者の話し合いで解決するのが原則です。しかし、相手方に離婚の話し合いに応じてもらえない、直接離婚について話し合える夫婦関係ではない、話し下手で権利主張することが苦手、専門家である弁護士のアドバイスを受けたい場合には、当法律事務所にご相談ください。
相続虎仏は、一度発生してしまうと、感情の対立が激しく、当事者同士ではなかなか解決できません。ケースによっては、法的な知識や複雑な事実を整理し、分析を要するものがあります。相続に関するトラブルを解決したい、予防したいという方はお気軽にご相談ください。


初回60分の無料法律相談を
行なっております。丁寧に状況を
聞き取り、問題解決を探ります。
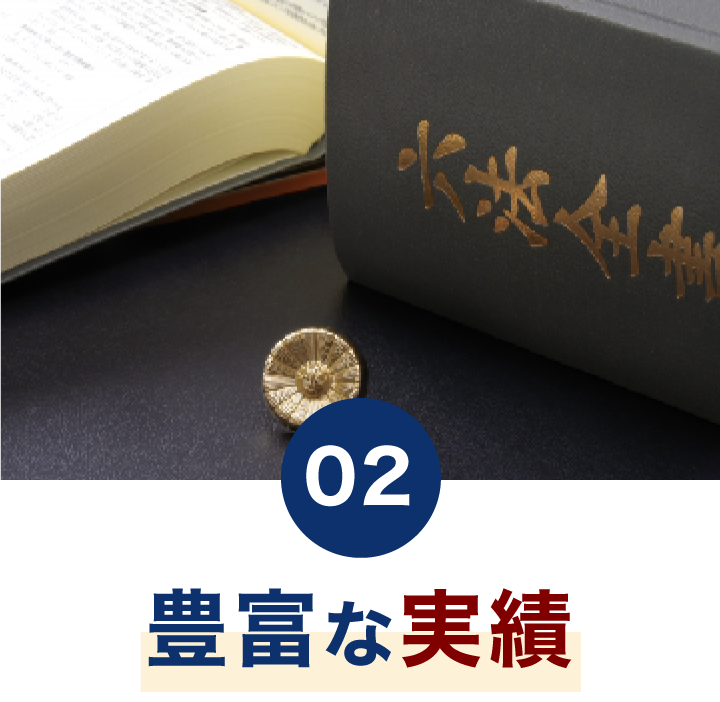
離婚・相続など豊富な解決実績の
ある事務所だからこそスムーズで
確かなサポートが可能です。

堺オフィスは堺東駅、
堺市役所から徒歩3分、
かに道楽の隣のビルです。
もしもの時に、安心して進めるための法律ガイド

これまでに四ツ橋総合法律事務所が培ったノウハウを基に、亡くなった直後から始まる複雑な手続きをわかりやすく一冊にまとめました。ご遺族が直面するであろう問題をシンプルかつ具体的にまとめ、円滑な手続きとトラブルの回避に向けたポイントをお伝えしています。
出版:東峰書房
価格:1,400円+税
著者:植松 康太、井筒 壱
監修:弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所